ここから本文です。
更新日:平成23年3月15日
![]()
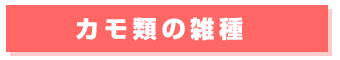 |
|
|
池や湖でカモ類の観察をしていると、おなじみのマガモ、カルガモ、コガモ、オナガガモ、ヒドリガモの中に“変なカモ”がいることがあります。 アヒルとマガモの交雑である「アイガモ」や、マガモとカルガモの交雑の「マルガモ」であったりします。 中でも一番よく目にする雑種ガモは、ヒドリガモとアメリカヒドリの交雑種です。 写真を見てください。奥にいるのがヒドリガモで手前がアメリカヒドリとの雑種です。 |
|
アメリカヒドリとは北米に分布するカモで日本には少数が渡来する珍しい鳥です。額から頭上が白く、目の後方が緑色、顔が灰色で、赤褐色のヒドリガモとは区別されます。 写真の個体はアメリカヒドリと言ってもよいですが、後頭部の茶褐色と顔の褐色斑にヒドリガモの特徴が出ています。 このようにカモ類は種間雑種が野外で観察されることが多い種類です。上記のほかにも、オナガガモ×トモエガモ、オナガガモ×マガモ、ホシハジロ×キンクロハジロ、コガモ×アメリカコガモなどいろいろな組み合わせが報告されています。 野外で、図鑑に掲載されていない“変なカモ”を見つけたら珍鳥発見と思わず、雑種ではと疑ってみてください。カモの世界もいろいろです。 |
|
 |
|
モズ(スズメ目モズ科)は江戸時代の書「本草綱目啓蒙」ではタカの仲間に分類されていました。 形態や習性からすれば無理からぬことと思われます。その鋭いくちばし(ワシタカと同じような鉤状になっている )で、昆虫類やトカゲ、カエルやクモなどのほか、スズメなどの鳥類やネズミ、ヒミズなども餌としています。地方名では「モズタカ」などと呼ばれています。 有刺鉄線やバラの刺などに、カエルやバッタが突き刺してあるのを見たことがあると思います。 これを「モズのはやにえ(速贄)」と言います。何のために、はやにえをたてるのかは諸説があります。 |
|
|
|
| など、いろいろな説があります。 貯食説では、実際に後から食べた例や、ひからびてしまい食べなかった例、他の鳥(カラスやトビなど)が食べてしまったなどがあります。 麻機遊水地では写真のネズミのほかに、スズメ、カナヘビ、カエル類、バッタ類、コオロギ類、シオカラトンボ、モツゴ(魚)、ジョロウグモ、アメリカザリガニのはやにえを確認しています。 モズは“はやにえ”以外にも不思議な生態をもつ鳥で、他の鳥の鳴き声を上手に真似ることが知られています。そのレパートリーは幅広く、ヒバリ、オオルリ、トビ、ウグイス、オオヨシキリなどです。時には救急車のサイレンを真似たという話もあります。 それもそのはずです、モズは漢字で「百舌」と書きます。さすが物まね上手です、百の舌を持っていたとは驚きです。 |
|



