ここから本文です。
更新日:平成23年3月15日
ホーム>麻機遊水地の自然>植物パンフレット
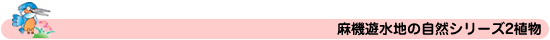
|
|
