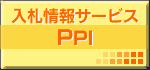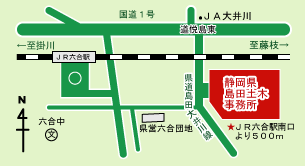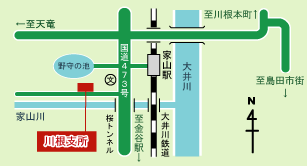ここから本文です。
安全について
島田土木事務所長 渡邉 良和
- ※所長室に、平成13年度静岡県芸術祭奨励賞受賞の焼津市石田としえさまの作品(風景画)が飾られました。所長室の品格が格段に向上した気がします。
寒い日、暖かな日の気温差が激しくなってきました。
一日一日、春が少しずつ近づいている気がします。
皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
今回は“安全”について、私どもの事務所の事例から考えてみます。
◆県道藤枝天竜線(島田市川根高日向)の道路斜面崩壊
既に新聞やニュースで報道されたように、2月10日21:10頃に、私どもが管理する県道藤枝天竜線の島田市川根町高日向地区内で道路の斜面が崩れ落ち、軽トラックが閉じ込められるという事故がありました。
2人が乗った軽トラックが、最初に崩れ落ちた土砂に行く手を阻まれ身動きが取れなくなってしまった後、助手席の方はドアを開けることができたので急いで車外に出て、わずかな明かりの中を転びながら、何とか土砂の上を通過して避難できましたが、運転席の方はドアが開けられず、助手席からの脱出を試みているうちに新たな土砂が積もり、土砂の山を乗り越えて避難することが困難になってしまったのだそうです。
閉じ込められてしまった方は、結局、通報で駆けつけていただいた消防署のレスキュー隊により助け出されましたが、この間、約4時間を暗く、寒い中で、不安を抱きながらお待ちいただきました。
お二人は、現在のところ、生命にかかわるような重大な傷害等はないとの情報をお聞きしていますが、道路を管理する者として深くお詫びを申し上げます。また、通行止めで影響を受けられる多くの皆さまにも、本当に申し訳なくお詫び申し上げます。
この現場では、9月の台風で小規模な斜面の崩壊があり、その後11月の豪雨の際にもその隣で、9月の崩落斜面を広げる形で新たに斜面崩壊が発生していました。私どもはその都度、交通止めを余儀なくされましたが、笹間地区の皆さまの唯一の生活道路であることから、斜面上の不安定な岩塊や土砂をかき落として、周辺も含めて斜面の安定状態を確認した後に道路上の土砂を排除し、万が一の落石等から通行車両を守るための防護柵を建てたうえで通行止めを解除してきました。
しかしながら、今回また新たに、11月の斜面崩壊をさらに広げる形の崩壊が発生しました。今回は、109ミリというまとまった降雨が2月6日~7日に降った3日後に斜面崩壊が発生したものです。一般に、降雨の最中や降雨直後に斜面が崩れることはしばしば見られますが、今回のように2~3日間の晴天を経た後にというのはまれな事例といえます。
このようなことがなぜ起こるのでしょうか。
斜面崩壊で露出した地盤を観察すると、風化した岩盤に細い亀裂が多く入り、斜面の最上部は岩が土砂状になっていました。今回は、2月6日~7日に降った雨が時間をかけて地盤内に浸透し、地中の最も弱い部分に達したときに崩れ落ちたという形が有力です。現場では当時強風も吹きましたので、それに揺さぶられた立木が表面近くの地盤を緩ませた可能性もあります。
では、このような崩壊を事前に予測することはできるのでしょうか。
それについては、私のこのコーナーの7月25日のページにも書きましたが、事前に精度よく予測するのは困難と考えています。7月25日のページを引用しますと、「道路や河川は、いわゆる工場製品と異なり、自然の地形や地盤の中に存在する、または造られた施設であるため、大雨などに対して強い部分と弱い部分が必ずあります。ただし、弱い部分といっても、初めからここがどの程度弱いと、必ずしもはっきりとは把握できない類の弱い部分ですから、当初の築造時には、費用対効果の発想からも、全てを完全に強く造っておくことは困難です。」
今回の現場では、11月の斜面崩壊の後に、上にも述べましたが、周辺のまだ崩れていない斜面も含めて地表を十分に点検し、安定性に問題がないことを確認したうえで通行止めを解除しました。
さらに安全を確保するために、これに加えて地中の隠れた部分の点検をすることも技術的には可能ですが、そのためには数十万円~数百万円の調査費が必要になります。現在、静岡県が管理する道路だけでも約2,700kmある中で、そのような調査を各箇所でし尽くすことは現実的に不可能に近いと思われます。そこで私どもは、日常的には各道路を毎月3回以上パトロールして、斜面の異常を示す落石などがないかを確認し、また、特に落石や斜面崩壊につながりやすい箇所については踏み入って点検を行うなどして、通行者の安全確保に努めています。
今回の現場については、原因究明と対策工法の決定を急ぎ、早急に安全で安心できる道路に復旧したいと考えています。皆さまにも、普段、通行された道路で落石を発見した場合などは、道路を管理する我々にご連絡をいただけましたら幸いです。なお、その道路の管理者が分からない場合には、市町にご連絡をいただければ、そちらから速やかに管理者である国や県に伝達される連携ができていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆工事中の安全
次に、私どもの事務所で発注している建設工事の安全についてです。
どのような労働においてもわが国では、労働の安全のために労働安全衛生法と呼ばれる法律を守らなければなりません。そして、「法」は基本的な事項を定めているものであるため、具体の内容は関連する「施行令」や「施行規則」等の規定を遵守することになります。
こうした中、先日、当事務所の発注している工事現場で問題が生じたのです。
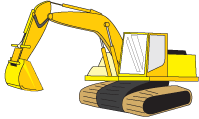
~ バックホウ ~
それは、作業者の安全のために作業の内容に応じて適正に使用することが義務付けられている建設機械を、正しくない用途に使用していたものです。具体的には、土砂の掘削や積み込みをするためのバックホウと呼ばれる機械(右図参照)を2台並べて、1台にはバケット(数本の爪がついた四角形のお椀のようなもの)を通常とは逆の上向きにつけて、その中に作業員を載せて木杭を保持させ、もう1台のバックホウには物をつかむアタッチメント(装具)をつけて、それをハンマーの代わりとして木杭の打ち込みをするという、建設工事に関わる人たちから見れば信じられないことをしていたのです。
これは、建設機械の目的外使用自体も不正ですが、作業者の身体のすぐ近くで、いつ杭の頭からずれるかもしれないアタッチメントを使って杭打ちをするのは、安全面から見て信じられない行為と言わざるを得ません。
そしてさらに、その工事現場に行った当事務所の監督員等が、その作業を見つけて是正を強く指示したにもかかわらず、数日後に再度現場に行った時にも、何ら是正することなく相変わらず危険な作業を続けていたのです。
皆さまは、このような業者に対してどう思われますか。
ハインリッヒの法則というものがあります。 これは、1件の重大な事故の陰には29件の軽度な事故があり、その陰にはさらに、300件の事故にはなっていないヒヤっとした場面があるというものです。多くの労働現場で取り組まれているヒヤリハット運動は、このハインリッヒの法則の事故には至らなかったヒヤリ事例をなくし、事故を防止しようというものです。各現場で日々努力されていると思います。
それに比べて、当事務所の今回の事例は何とも言う言葉がありません。
世の中では事故が実際に発生すると大きく騒がれ、重大なペナルティが課されるというのが一般的で、それに対して、今回のような事例では、ほとんど組織の内部で収まってしまうことが多いものです。
しかし、今回の施工業者の行為は、特に、一度注意されたことを無視し不正な行為を継続していたという点で、極めて悪質で許しがたいものと思っています。安全に留意していてもわずかな隙で起こってしまった事故に比べて、事故こそは起きていなくても、はるかに自己責任が重いと考えています。
私が職員にいつも伝えている、“県民目線に立って、県民の皆さまに満足していただける仕事”を社会資本の整備や管理の場面で実際に行うためには、仕事を請け負っていただく業者の皆さまと我々との間で、信頼感を持ち合うことが非常に大切です。共に協力していいものをつくろうという意識こそが、まさに根幹と言えるものです。
そのような意味から、この事例は、あるべき発注者と工事請負者の信頼関係につばを吐くものといえます。
私どもは、このような事例には今後も毅然とした態度で臨み、皆さまのご期待に沿える行政を進めていきたいと思います。ご支援をよろしくお願いします。
インフルエンザが全国的に猛威をふるい、特に子供たちへの感染が多く学級閉鎖も増えているようです。公衆の場所、ご家庭内、どちらにおきましても予防に細心の注意をお願いします。
それでは、次回まで、皆さまお元気でお過ごしください。
平成24年2月14日
島田土木事務所長 渡邉 良和