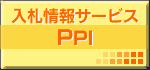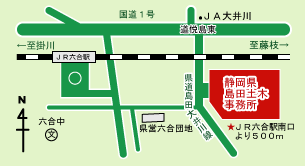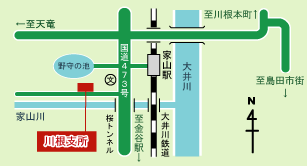ここから本文です。
新東名高速道路の開通と坂口谷川の津波対策
島田土木事務所長 渡邉 良和
- ※写真は1月に牧之原市で行われたリバーフレンドシップの調印式の時の様子です(一番左が筆者)
年が替わり、早くも1カ月が過ぎました。
繰り返しの寒波襲来で、全国的に低気温や記録的な積雪が見られていますが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
さて、今回は、待望久しい新東名高速道路の開通と、坂口谷川における津波対策のお話です。
◆新東名高速道路の4月14日開通が決定!
去る1月27日に、中日本高速道路株式会社(略称;NEXCO中日本)は新東名高速道路の静岡県内区間について、今年4月14日15時に開通させると発表しました。計画が動き出してから開通までに約20年の年月を要したこの道路の正式呼称「新東名高速道路」は、少し前までは「第2東名高速道路」の名称で建設が進められていたため、多くの皆さまには“第2東名”の呼称がおなじみかもしれません。
建設事業に着手した後に事業者である日本道路公団が分割、民営化され、現在はNEXCO中日本が県内区間の工事を進めていますが、民営化されたときに公表された開通予定時期を約1年間早めての開通です。NEXCO中日本の皆さま、本当にありがとうございます。
今回開通する区間は、御殿場JCT(ジャンクション)で現東名と分岐するところから浜松いなさJCTまでの本線部分が144.7km、これに浜松いなさJCTから連絡路を通って三ケ日JCTで現東名に接続するまでの区間12.7kmと、清水地区で新・現東名を接続する連絡路の延長4.5kmを足し合わせて、開通総延長は162kmになります。 *下に図があります
この162kmという開通延長は、わが国の高速道路では1度に開通した延長として突出した第1位で、おそらく今後も破られない記録になるだろうといわれています。
この新しい高速道路の開通は、その1度の開通延長が長いことも含めて、本県や国全体に対して非常に大きなインパクトを与えるもので、今後に大きな期待を抱かせるものです。
新東名の特徴や期待される効果については、既にNEXCO中日本などからさまざまな情報の提供があり、ご存知の皆さまが多いと思いますが、主なものを復習してみます。
-
新東名は、現東名に比べてはるかに走りやすい
まず、道路のカーブがゆるくて直線に近いものになっています。カーブの最小半径は現東名では300mですが、新東名の県内区間では3,000mとなっています。皆さまが高速道路を走ると、カーブが急なところでは路側に“R=500”などの標示がありますが、この“R”は英語の“radius”の略で“半径”の意味です。R=500は半径500mの円に沿って走る形の道路という意味です。
次に、道路の勾配も非常にゆるいのが特徴です。現東名では最急勾配が5%であるのに対して、新東名では2%です。ちなみに“勾配”は英語で“inclination”といい、皆さまが路側で見かける“I=7%”などの標示は、急勾配の道路で、スピードやフットブレーキの使いすぎに対する注意を喚起するための標示です。また、7%とは、水平に100m移動したときに7mだけ高さが増すという意味の勾配表現です。
新東名はこのような構造の道路ですから、運転者の快適さはいうに及ばず、燃費の節約にもつながると、物流業界の方々からも大いに期待されています。 -
東名高速道路が2本になり、現東名の日常的な渋滞が解消する
現東名の1日の交通量は8万台近くになります。もともと5万台以下の通行を想定して設計されているため、ゴールデンウィークやお盆の時期などに限らず、日常的に渋滞が発生するのは当然と言えます。設計時には、その後の急速な自動車交通の進展は予測できなかったのでしょう。
新東名ができれば現東名の交通量がおおむね半分になり、渋滞は解消すると考えられています。新東名についても、現東名に比べてはるかに走りやすい道路であるために、現東名以上に渋滞の恐れがありません。 -
新東名は、大規模地震や津波、高潮などの影響を受けにくい
本県では東海地震や東海・東南海・南海の三連動地震による被害が強く危惧されていますが、新東名は現東名に比べて山沿いを走っているため有利な点がいくつかあります。たとえば揺れの強さでは、東海地震の第3次被害想定の震度分布図を当てはめたとき、現東名が震度6強のエリアを多く通過し、震度7のエリアも一部通過しているのに対して、新東名では震度6弱のエリアが多く、震度7のエリアは全く通過しないという違いがあります。地盤の液状化の可能性が高い地域の通過も、新東名では激減します。これらは、一般に山地部に入るほど地質がよくなることによります。また、津波に対しても、新東名は内陸部を走るので心配がありません。
さらに、現東名の富士~清水間では、海岸線を通過しているために台風襲来時などを中心に道路が波をかぶる、またはその恐れがあることから、しばしば通行止めが生じていますが、新東名ではその恐れがありません。 - 新東名により、本県の内陸部の開発と、それによる地域の活性化が期待される
新東名はこれまであまり土地が高度に利用されていない内陸の中山間地を走るため、新たな開発を誘発する期待があります。観光、工業、物流などの産業のほか、特に、農産物産地から大都市圏への輸送という面でも利便性が増します。
そして、沿海部の皆さまにはつらい話ではありますが、津波被害のリスクに対応しようとする県内の諸企業が施設の移転を考える時に、県外への移転ではなく県内の内陸部に留まっていただく要因ともなり得ます。また逆に、県外の企業に沿海部などから移転していただく、あるいは新たに起業していただくことも考えられます。
ただ、これらの新たな土地利用を可能とするためには、まだまだ土地利用規制がハードルとなっています。県や市町では、国に対して関連する規制を緩和するよう働きかけていますが、まだ解決が見えていません。これらの課題は新東名が計画されたころからほぼそのまま残っているものであり、無駄な時間を過ごしてしまっているというのが実感です。
このように、新東名が現東名に比べて有利な点が多いのですが、一方で現東名は、既に経済活動が盛んに行われている人口密度の高い地域を通過していることから、短距離移動など、比較的に狭い範囲の経済活動や日常の使い勝手からは有利です。
新東名と現東名が並行して走ることは、大災害発生時などの移動・輸送に際し、複数のルート選択を可能とするものであるとともに、交通事故の発生なども含めた不測の事態に対しては、相互に補完しあえるということに大きな価値があるのです。
また、開通して40年以上が経過した現東名では、毎年秋に集中工事期間を設けて大規模な補修が行われていますが、その補修では必ずしも十分ではないと聞きます。また、工事期間内は、わが国の大動脈にふさわしくない深刻な渋滞も発生しています。新東名が開通すれば、現東名を大規模に通行規制して本格的な補修・補強をしても、現東名1本のみの場合に比べて渋滞の心配は大幅に軽減されることが明らかです。
新東名開通の意義について、主なものを復習してみました。
4月14日の開通により静岡県の各地域が、そして全国が、大いに元気になってくれることを強く祈念したいと思います。
◆新東名高速道路の、その他の区間の様子
新東名の静岡県内区間は4月14日に開通するのですが、その他の区間はどのような状況でしょう。
まず愛知県側では、既に、豊田東JCTから名古屋港の上空を経由して四日市JCTまでの間が開通しています。名古屋港を通過するときに、名港トリトンと呼ばれる3つの美しい橋を目にします。これらの橋は橋の途中に塔(タワー)が立てられ、そこから束ねられたピアノ線を斜めに何本も張って橋げた(通行する部分)を吊る構造で、斜張橋という形式です。
今後、2014年度には、浜松いなさJCTから豊田東JCTまでの間が開通予定であり、新東名の西側がつながります。
一方、東側では、まだ開通した区間はなく、現在、建設段階です。開通時期は、新東名の起点となり、首都圏中央連絡自動車道(略称;圏央道)に接続する神奈川県の海老名南JCTから、厚木南IC(インターチェンジ)までの間が2016年度、厚木南ICから伊勢原JCTを経て伊勢原北ICまでの間が2018年度、最後の、最も長い伊勢原北ICから御殿場JCTの間が2020年度とされ、結局、東側がつながるのは2020年度ということになります。なお、現東名とは伊勢原JCTで接続し、海老名南JCTからも圏央道を経由して現東名に移ることができます。
このように、新東名の全線開通は2020年度ということになりますが、1年でも2年でも開通時期が早まることを期待しましょう。
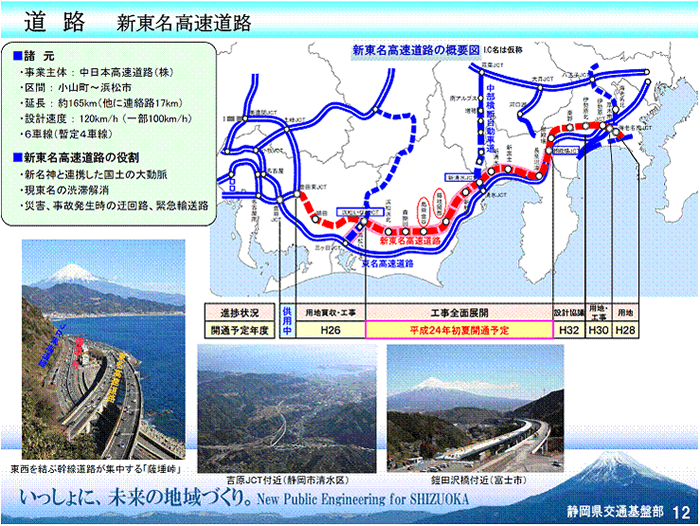
◆坂口谷川の津波対策
この1月31日には、静岡市内で静岡県河川審議会が開催されました。
私どもの事務所で管理する坂口谷川の河川整備基本方針も案件の1つでした。
富士山静岡空港の南方から流れを発し、吉田町の駿河湾に注ぐ坂口谷川については、地域の皆さまから、津波対策水門の整備を悲願としてご要望をいただいています。
当事務所が管理する河川は14河川(水系)ありますが、そのうち津波対策が必要な河川は7河川です。東から瀬戸川、栃山川、湯日川、坂口谷川、勝間田川、萩間川、そして須々木川です。このうち、これまでに5河川の対策が完了し、現在整備中の勝間田川水門は、来年の春には完成予定です。対策未着手の残りの1河川が坂口谷川です。
坂口谷川の水門建設が最後になった理由は、平成13年に行われた東海地震の第3次被害想定で、当地区の津波高が3.1mとされているのに対して、現在の堤防高が3.4mと、わずかですが高さに余裕があったために優先順位が低かったためです。
しかしながら、現地へ行くと、坂口谷川周辺の海岸堤防の高さはすべて6m余りとなっています。坂口谷川の河口のみが周りに比べて3m近く低くなっているということです。これは、東海地震の対策に着手した初期段階の第1次被害想定で、津波高が各地区ほぼ一律に6m程度と想定されたことや、50年に1度程度発生するレベルの高潮の対策として高さ6m余りの堤防が必要とされることから、これまでに海岸堤防が先行して整備されたというのが理由です。
今までは、国や県の予算状況が厳しいからと、坂口谷川水門の整備の遅れにご理解を示していただいた地域の皆さまにも、このような現地の状況を日々目にされている中で、昨年3月11日に発生した東日本大震災における津波の様子をテレビで目の当たりにされた時には、計り知れない危機感が生まれたことは当然のことと思います。
このたびの河川審議会においては、私も発言の機会を頂戴したため、こうした現地の状況や地域の皆さまのお気持ちを、強く、審議会委員の皆さまにお伝えしたつもりです。
水門建設などを含む各河川の整備に当たっては、整備の基本方針や計画を、河川審議会など外部の人たちの意見を聞きながら定めたうえで実施するよう、河川法で義務付けられています。坂口谷川の場合、この手続きにしたがって作業を進め、整備計画の策定が完了するのは手続きを大急ぎで進めても平成24年度末頃と見込まれます。
地域の皆さまからすれば、もどかしいという思いを禁じ得ないと思います。
そこで、平成24年度には整備計画策定と並行して、計画策定後に手戻りが生じない範囲で、水門の建設をできるだけ早めるために必要な調査や現地測量を進めることができるよう、現在、本庁と私ども事務所とで調整を行っているところです。
何とか予算を確保して、地域のご協力もいただきながら、1日でも早い水門の建設につなげたいと考えています。
さて、今回は、いま大きな関心が寄せられている2つの話題を取り上げてみました。ご参考になれば幸いです。
インフルエンザが猛威を振るい始めています。皆さまも十分に注意され、お元気でお過ごしください。
それでは、またお会いしましょう。
平成24年2月2日
島田土木事務所長 渡邉 良和