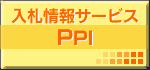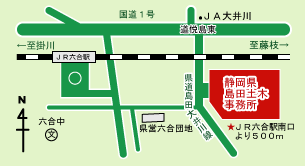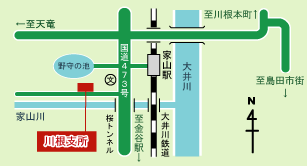ここから本文です。
社会資本の役割と現状、将来
島田土木事務所長 渡邉 良和
- ※写真は昨年12月に焼津市で行われたリバーフレンドシップの調印式の時の様子です(一番左が筆者)
皆さま、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
今年のお正月は天候に恵まれ、国内で大きな事件や事故もなく、穏やかな年明けとなりました。私ども土木事務所におきましても、年によっては降雪の為に道路が通行止めやチェーン着装の規制となり、道路利用者に向けた情報の発信や、除雪作業をしていただく業者の皆様との連絡調整のために、職場に出勤を余儀なくされることがあるのですが、今年はお蔭さまで平穏に過ごさせていただきました。
また、高校サッカーではわが郷土の代表「清水商業高校」も2戦勝ち抜き、少しの間でしたが夢を見させていただきました。選手諸君はお疲れ様でした。また、頂上を目指して、県内各校が競い合っていただきたくことを期待しています。
◆東日本の復興と我々の危機管理
ところで、私は、今年の年賀状では“おめでとうございます”という趣旨のご挨拶は遠慮しました。昨年の秋から年末にかけて、マスコミに登場する東日本大震災で被災された地域の皆さまの、「被災から何ヶ月も経つのにこんな状態では、新年を迎えてもおめでとうどころではないよ。」という言葉を、何度も見たり聞いたりしていたからです。
福島第1原発の影響範囲も含めた被災地の早期復興に向けて、自分自身の立場で何ができるのだろうかと常に自問自答し、いくつもメニューは頭に浮かぶのですが、なかなか実現につなげられる直接的な行動メニューが見つけられないでいます。しかし、被災地の遠くで暮らす多くの国民が、個々に、あるいは連携して、現地の皆さまの現状に想いを致しつつ、復興に向けて何ができるのかを常に考え、できることから実行しようという意識を持つことが、今までは他人事であった人にとっても、まずはスタートラインに立つことであると思っています。
一方、本県に直接かかわる自然災害に対する危機管理については、これまでも、今後も、私ども土木事務所は直接的に大きな責務を負っています。
東海地震そのものや、東南海、南海地震との連動地震が危惧され、現在、国レベルで津波規模などの検討が行われていますが、その地震対策に加え、昨年多く発生した台風、大雨による道路の斜面崩落、路肩決壊、山地の土砂崩れ、そして河川の堤防や護岸の決壊などに対する対策です。
これらには事前の対策が何より求められるところですが、時間的、予算的に事前対策が十分に取れない部分に対しては、ソフト対策や事後の対応策が極めて重要となります。私どもは常に、それらの準備や訓練に努めています。
◆身近な社会資本の現状
さて、私は、このお正月に磐田市内にある妻の実家に行ってきました。
私の自宅は島田市の旧金谷町内にありますので、ルートは国道1号の島田金谷バイパスから日坂、掛川、袋井、磐田の各バイパスを経由して行きます。道中は高架構造の区間が多いのですが、掛川市から袋井市に入る辺りは4車線で歩道が設置された平面の道路となっています。そして、そこを車で走りながら強いショックを受けたのです。
それは、道路脇の雑草と植樹帯の状況です。
皆さまがいつも利用される道路には、東名高速道路などの中日本高速道路株式会社が管理する有料の高速道路と県の道路公社が管理する有料道路、現在整備中の伊豆縦貫自動車道のような国や県などが管理する無料の高速道路、そして、皆さまに最も身近な多くの無料の国道、県道、市町村道があります。
そして、この道路網の大部分を占める無料の国道、県道、市町村道は、皆さまからいただく税金で草刈りや舗装の補修などの維持管理が行われているのですが、これらの道路の中で、これまで最も維持管理が行き届いていた国が管理する国道において、道路脇の雑草が刈り取られないままの姿や、お正月の時季でも剪定されていない植樹帯が目に入ったのです。
このような十分な維持管理ができていない状況は、私どもが管理する県道などにおいて、予算の逼迫により残念ながらときどき発生していました。しかしながら、国の管理する道路では初めて目にした気がします。
他方、河川についても同じような状況があります。
私どもが管理する河川では、昨年も、「河川内に堆積した土砂が洪水の発生につながる恐れがあるので、昔のように掘削して排除して欲しい。」というご要望を、管内の多くの皆さまからいただきました。あるいは、「川の中の立木が成長して流れの邪魔になっている。県の予算がなければ地域の住民で草刈りをすることも一部ではできるが、立木の伐採処理までは無理だ。県でお願いしたい。」という声も何度もいただきました。
昔はもう少し頻繁に堆積した土砂の排除ができていましたが、最近は予算が十分に確保できず、堆積土砂の排除と河川内立木の伐採を、各箇所の状況に応じて緊急性の高いものに絞って予算を振り向けているのが実情で、施工できる箇所の数も含めて住民の皆さまのご要望を満たすレベルにははなはだ遠いものであると感じています。
これらの道路や河川の維持管理に、近年の公共事業費削減の影響が明確に現れていると感じています。
◆“この国のかたち”をどうするか
また、近年、各地域の今後のまちづくりを議論すると、必ず、「コンパクトシティ」づくりに向けてという方向が示されます。
「コンパクトシティ」というのは、次のようなものです。
今後、高齢化がますます進むと、買い物ができる場所はもちろんのこと、病院や学校や銀行やその他もろもろ、生活に必要な施設をすべて狭い範囲に集めるのが暮らしやすい環境となる。郊外の各地区に似たような施設をいくつも造ったり、各地に散らばる住民のために道路を整備し続けたりすることは無駄である。国や地方の財政力が今後ますます乏しくなる中では、これが当然の方向だ。
皆さまは、この考え方をどのように感じられますか?
おそらく、多くの方が賛同されると思います。私も、非常に的を得た発想だと思っています。
しかし、いつも、それだけで議論が終わってしまっているのが残念です。
わが国は他の先進諸国に比べて国土の可住地面積が狭く、ある意味ではそれだけでコンパクトなまちとも言えますが、国土の都市部と地方部には、それぞれ住民が生活をしています。主に中山間地に住む人たちが常に山の様子を肌で感じ、その直接、間接の情報をもとに変状が小さなうちに対策を施し、国土が保全されている実態があります。
仮に将来、すべての地域でコンパクトシティに集約されたとしたら、その中に住む人たちには便利で暮らしやすいかも知れませんが、「田舎」はどうなるのでしょう。田舎にはだれも住まなくなって山が荒れ放題、土砂崩れが頻繁に起こるようになり、崩れた土砂が川に溜って、地方部でも都市部でも洪水が起こりやすくなるという想像は、決して大げさではないと思います。
住民の移動にかかせない道路に目を向けてみれば、東日本大震災で思い知らされたような緊急避難、緊急支援のためという役割の前に、日常的には、都市と田舎が相互に助け合って暮らすツール、あるいは地域間の連携のためのツールという役割があります。しかし、そのような道路の整備は財政が厳しい中では費用対効果に乏しく、これからは維持管理をするだけで手一杯、建設、改良はあきらめるべきだ、という議論が、現在、大きな力を持っています。
維持管理費が不足しているうえに、さらに、国土の将来に必要と考えられる整備費も、それ以上にカットされようとしているのです。
「コンパクトシティ」の議論には、必ず「田舎」がセットで議論され、将来の国土全体をどうして行くのかという方向性が議論されなければならないと思います。そして、そのような議論がなされれば、「コンパクトシティ」に加えて、地方部のために真に必要な施策と、それに必要な予算も用意しなければならないという結論になるはずです。
◆公共事業予算
国の平成23年度の当初予算は、一般会計と特別会計を合わせて220兆円、そのうち、国債の利払いなどが37%、年金、医療関係費が34%を占め、公共事業費は5兆9千億円で3%にも満たないという新聞記事が、昨年、出ていました。
上に挙げた社会資本の現状の事例はほんの一部ですが、こうして見てきますと、各年度に編成される予算において、近年、社会資本の全体には目が向けられず、必要性が必ずしも高いとは思われない一部の公共事業が過大に取り上げられ、その雰囲気の中で、公共事業費全体が常に予算総額の調整に安易に利用されてきたということが、よく理解していただけると思います。
国も地方も財政的に厳しい中であるからこそ、それぞれの分野の実状がどうであるか、真に必要な予算はどの施策で、そのためにいくら必要であるのかを、もっと全体を見てしっかり議論する必要があるのではないでしょうか。そして、本当に必要な予算の規模と、それを確保するための歳入の仕組みを、国土全体の将来を見据えて、みんなで議論すべきではないでしょうか。
皆さまの活発なご議論と、情報発信を期待したいと思います。
それでは、厳しい冷え込みが続いていますが、皆さま、お元気でお過ごしください。
また、お会いしましょう。
平成24年1月6日
島田土木事務所長 渡邉 良和