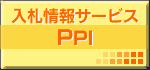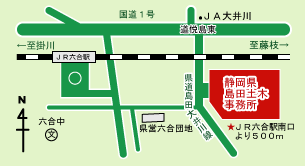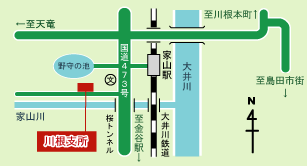ここから本文です。
災害復旧の対応状況と年末のごあいさつ
島田土木事務所長 渡邉 良和
※写真は12月22日撮影
「メリークリスマス!」
クリスマスイヴには少しだけ早いのですが、今年も残すところ、あとわずかとなりました。厳しい寒さの中、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
今回は、この1年を振り返るとともに、当事務所における今年の災害対応状況についてご報告します。
◆この1年を振り返って
この一年を振り返ってみますと、何といっても3月11日に発生した東日本大震災と福島原発の事故が強烈な印象で、これは間違いなく、現代史に刻まれるものでしょう。本県に直接の被害はないものの、福島原発事故に起因する風評被害は本県でも多方面に及び、今後しばらくは、その影響が続いてしまうことが心配です。
また、本県では、3月15日深夜に、富士宮市の震度6強を最大とした地震がありました。激しく揺れた同市内では、墓石や石灯篭の転倒、家屋の屋根瓦の損傷が多く見られましたが、私ども土木事務所や県の関係部局でも、職員が、一時JRが不通となる中、真夜中に必死の思いで参集先の県の職場に駆けつけました。
この地震は、東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震に誘発されたもので、富士山火山活動に関係する地震の可能性があるとの指摘もありました。
地震以外にも、全国的に、台風6号、12号、15号などの大雨や強風により大規模な被害が発生し、本県における被害も、最近にない箇所数、規模に達した1年でした。
以上、私どもの業務に関連の深い事項を挙げてみましたが、今回は、皆さまに特に身近な公共施設について、当事務所における被災後の復旧に向けた取組みの現状をお伝えしたいと思います。
◆島田事務所の災害復旧事業
当事務所における公共土木施設災害は、河川22箇所、道路13箇所、砂防(河川)1箇所、これらをすべて合せて、被害総計は36箇所、14億円余に達しました。
このうち、既に現場で工事がかなり進んでいるものも含め、年末までに復旧工事の契約を締結(予定を含む)したものが25箇所、年明けに契約予定のものが5箇所、その後、工期が来年度にまたがるために、12月県議会で事前に債務負担行為の承認をいただく必要があったものや、他機関との事前協議に時間を要しているものなどを契約して、それぞれ早期に復旧工事を完成させるよう努めてまいります。
道路の災害箇所につきましては、現場ごとに早期の交通開放を目指して作業を行いましたが、大規模な斜面崩壊を受けた箇所などでは、通行止めの解除までに長期間を要したほか、一部では、現場の状況から仮設防護柵を設置して交通開放をする方策がとれないために現在も通行止めが続いているなど、皆さまには大変ご迷惑をお掛けしています。深くお詫び申し上げます。
道路は日常生活の中で、常に、安全、円滑に通行できることが求められている施設ですので、それぞれの箇所が1日でも早く万全な状態でご利用いただけるよう、工事請負業者の皆さまとともに最大限の努力を重ねてまいりますので、何卒、ご理解をお願いします。
一方、河川や砂防河川の災害箇所につきましては、これから大雨の心配が少ない季節となりますので、この時季に作業を急ぎ、来年の出水に備えることとしています。
さて、今年発生した災害箇所の、現在の対応状況は以上のとおりですが、実は、これら以外に1件、まだ復旧計画自体が固まっていないものがあります。
それは、藤枝市蔵田地内の県道藤枝黒俣線の地すべりです。
◆地すべり対策の難しさ
蔵田の地すべりは、元々は平成16年の秋に、道路パトロールで路面に比較的小さな亀裂ができたのを発見し、地すべりの初期症状の疑いが認められたことから、その後、これまで継続してボーリング調査や地表面の観測を行い、地中や地表の動きを監視し続けてきました。
そして、今年の8月までは目立った動きはありませんでしたが、9月5日の台風12号による降雨が直接原因となって、道路面に30㎝ほどの段差が生じ、車の通行ができなくなってしまいました。地盤の動きはその後も続き、路面の段差が1.0m近くまで広がった後、現在は雨の少ない時季となって小康状態といったところです。
この現場では、なぜ復旧計画の策定が遅れているのか。
それを理解していただくためには、地すべりのしくみを理解していただく必要があります。
地球上のどこでも、その場所が地すべりを起こしやすい場所であるかどうかは、地質や地形の状況に大きく左右されます。しかし、地すべりを起こしやすい場所であっても、実際に地すべりが起こるかどうかは必ずしも明確には予測できません。地すべりが起きるのには、一般的に、地下水位が高くなることが引き金となります。その仕組みは次のとおりです。
地下水位が高くなると、地中の土砂や、亀裂が多く入った岩塊が水を含んで重くなります。そして、水が無い時は土や岩の粒同士がしっかりかみ合っていたものが、水に浸かったことによって浮力が生じ、かみ合う力が弱くなります。こうして、地盤のどこですべりが起こってもおかしくない状況が生じ、地形や地質や地下水位の条件から、より滑りやすい場所で地盤にずれが生じるのが地すべりなのです。
このため、地すべりの対策は、実際に滑った後にすべり面の位置と滑る土塊の範囲を的確に把握し、滑り落ちようとする土塊の重みに対して、引き止める力を加えることになります。具体的には、滑り落ちようとする土塊を、束ねたピアノ線ですべり面の奥の動かない地盤につなぎとめる方法や、すべり面を貫通して鉄筋コンクリートなどの杭を建て込み、ずれなくする方法があります。
ところで、すべり面は必ずしも1つではなく、同時に複数生じることが多くあります。
仮に、深部にすべり面があることを見落として浅い部分の地すべり対策を行った時には、つなぎとめたはずのピアノ線や鉄筋コンクリート杭などが、動かないはずと考えた地盤もろとも動き出して、対策が全く意味を持たないものとなってしまいます。
また、逆に、実際に滑っていない、考え得る最も深いすべり面で対策を行えば、それは経費の大きな無駄遣いにつながる可能性があります。
1つの現場で数千万円から億円単位に及ぶことも珍しくない地すべり対策においては、やはり、わずかでも動いているすべてのすべり面を把握し、適切な対策を行う必要があるのです。
来年の初夏に開通予定と発表された新東名高速道路の県内区間の工事においても、最後は、動きの全容を把握するのが困難な地すべりの対策の進捗状況が、完成時期を大きく左右することになったと伺いました。
蔵田の地すべりでは、これまでに継続して調査・観測を行い、すべり面を部分的には把握しましたが、滑る土塊の範囲がまだ確実にはつかめていません。このため、新たな観測機器を設置し、地すべりが再度動き出す来年の春から夏過ぎまでの間にしっかり観測して、的確な対策(復旧)計画を策定する予定です。
大変ご迷惑をおかけしていますが、もう少しお待ちいただきたいと思います。
◆よいお年をお迎えください
このコーナーを6月に始め、半年あまり経過して年末となりました。今年はこれが最後のページとなります。
その時季に思いつくままに、県民の皆さまに情報をお伝えしてきましたが、お読みいただきました皆さまに心から感謝申し上げます。
来年は、もっともっと良いことが、いっぱいありますように!
それでは、新年に笑顔でまたお会いしましょう。
それまで、皆さま、お元気でお過ごしください。よいお年を!
平成23年12月22日
島田土木事務所長 渡邉 良和