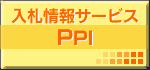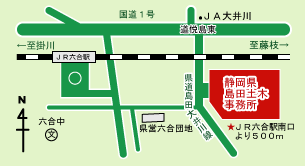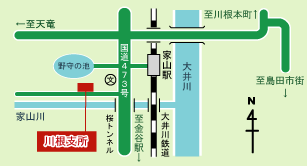ここから本文です。
東日本大震災の実情と県の補正予算
島田土木事務所長 渡邉 良和 

- ※写真は11月25日に川根本町で行われた円卓会議(県事業に関する県と各市町の情報交換会)の様子です。(右列の右から2番目が筆者)
このところ、気温の極端な上下変動が続き、私は少し風邪気味になってしまいました。皆さまはお元気でお過ごしでしょうか。 今回は、東日本大震災の現地の実情と、静岡県の今年度の地震・津波対策補正予算のお話です。
◆東日本大震災の現地の実情
前回の“所長のことば”で、私どもが10月中旬に東日本大震災の現地を視察・調査してきたことについてお伝えしましたが、タイムリーにも、この12月2日に静岡市内で、仙台市で建設業を営む深松努氏(社団法人仙台建設業協会副会長)による、今回の地震・津波発生時の住民の状況や、震災後にがれきの撤去などにかかわってこられた建設業の皆さまの実情に関する講演がありました。
私は、自分の眼で現地を見て感じた印象や疑問点の上に立って、被災地の真の姿をさらに正確に理解するためにはこの上ない機会ととらえ、聴講させていただきました。そして、講演の最後の質問時間に、自分の感じていた疑問を率直にぶつけてみました。
講演では深松氏が、地震や津波に対して二度と人命を失うことがないように、また、今後、万が一被災してしまった場合に、建設業者として住民のために、より的を得た対応ができるように、東海地震が危惧されている静岡県民の立場にも触れながら、熱くアドバイスをしてくださいました。また、私の質問に対しても真摯に答えてくださいました。
そして、その中で、以前から私が感じていた大きな疑問が解けました。
私の1つ目の疑問;「がれきの片づけがまだまだ残っているのに、現在現地で作業している重機や作業者の数が少ないのはなぜ?」に対して、実情は、「他の都道府県から業者の支援を頼みたいけれども、現地での宿泊費などの経費が支払われないため頼むに頼めない。」
2つ目の疑問;「がれきが片づけられている一般住宅地にコンクリート基礎だけがそのまま残っているのはなぜ?」に対しては、私どもが現地で推測したとおり、「基礎を撤去してしまうと土地の境界が分からなくなってしまうから」でした。
そして、深松氏は私の質問に対する回答の中で、「長年の公共事業縮減の流れの中で業界の経営は極めて厳しく、地元では業者数が半分になっている。他県では業者数がそれほどの減少ではないかもしれないが、どこでも1業者が抱える人数は激減している。実態として、鉄筋コンクリートの鉄筋を加工し組み上げる鉄筋工や、型枠工を始め、専門技術者がどんどん仕事を辞めているため、業界は瀕死の状態である。今回の震災は20兆円規模の被害額だが、被害額80兆円と見込まれる東海・東南海地震が起これば、業界がこのままの体力では復興に対処できない。」と説明してくださいました。
この内容は、私が以前からこのコーナーなどで示してきた、震災や大雨、洪水による被害が起こった場合は、自社で重機を所有し多くの技術者や作業員を雇用している体力のある業者の力が必ず必要であり、そのためにも、しかるべき公共事業費規模の確保が必要という認識と全く同じ視点で、同感であることを氏にお伝えしました。
わが国の建設業者数は10年ほど前のピーク時には60万社でしたが、現在は、減少して50万社程度になっていると思われます。
以前、バブル経済がはじける前に、わが国の建設業者数は多すぎて非効率という議論があり、西欧諸国を基準にすれば10万社以下が妥当だというコメントを目にしたことがあります。
その後、公共事業費が半分以下になり、民間投資も冷え込んでいる現状では、業者が多すぎて過当競争になり、結局、低入札受注が増えて、下請けも含め大多数の業者が自社で重機を所有する体力を維持できないという現状につながっています。仮に、今後、公共事業費をいくらか増やすことができても、効果は限定的でしょう。
現在の経営環境から、使用する重機のほとんどをリースでまかなっている業者が大部分を占めるという現状の中で、重機を保有し、常用の技術者・作業者を雇用して、非常時に真に活躍のできる業者を増やしていくためには、建設業に関連する制度を見直し、業界を再編する必要もあるのではないでしょうか。そして、それにはもちろん、幹である国の産業・経済構造に手をつける必要があります。
他方、戦後に多く造られたものを中心とした多くの社会資本の維持管理に必要な予算が、急速に増加しており、また、わが国の将来を見据えたとき、維持管理にとどまることなく、国の発展につながる新たな社会資本投資を堅実に行っていくことも間違いなく必要です。それらに必要な公共事業費をしっかり確保することも、健全で体力のある建設業者を育成し、守ることにつながります。
さて、近年の不安定なわが国の政治が、このような問題に真剣に取り組んでくれるのはいつになるのでしょうか。やはり、より多くの国民に気づいていただき、みんなでもっともっと声を大きくしていくしかないのではないでしょうか。
◆地震、津波に備えた県の補正予算
本県ではこれまでも、地震や津波に備えた対策に力を入れてきましたが、今年度は、今年3月11日の東日本大震災を踏まえ、対策を急ぐための補正予算が組まれています。
補正予算には、既にこれまでの県議会で成立したものと、現在会期中の12月県議会に上程されているものがあり、12月県議会に上程されているものについては詳細な事業箇所などは未確定ですが、今年度、補正予算で対策を予定しているものの主な概要は以下のとおりです。
○道路の橋梁耐震対策
緊急輸送路上の橋梁について、地震で橋が壊れない(落ちない)ようにする耐震対策をこれまでの計画を前倒して実施し、対象橋梁全体の対策完了時期を前倒し
○道路斜面の落石対策
地震発生時に斜面からの落石や斜面崩壊の発生が危惧される箇所で、被害を未然に防止するために斜面を補強
○河川堤防の液状化対策
地震による地盤の液状化で、特に津波に対して堤防の機能が失われる恐れがある箇所について、液状化が起こらないように地盤を補強
○水門の耐震補強に向けた設計
津波に備える水門について、これまでの設計よりもさらに大きな地震に耐えられるように耐震性を向上…設計が終了後、工事実施(次年度以降)
○水門遠隔操作施設の高度化
これまで津波の恐れのある場所から遠隔操作していた水門について、津波の心配のない場所から遠隔操作できるように改善
○急傾斜地崩壊対策事業
地震発生時などに斜面崩壊や落石から住宅を守る施設(擁壁など)について、これまでの整備計画を前倒しして実施
○津波避難用施設の整備
津波避難の際、急傾斜地崩壊対策等で整備された擁壁の上に上がるための階段や通路の整備
当事務所における、今年度補正予算による事業実施箇所は後日あらためてお示ししますが、今後とも、地震・津波対策を精力的に進めていきます。
それでは、今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆さま、お元気でお過ごしください。
平成23年12月7日
島田土木事務所長 渡邉 良和