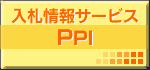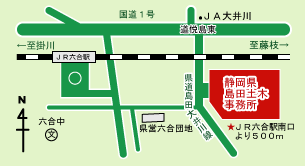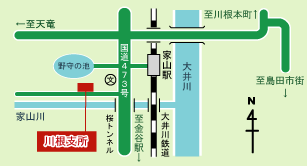ここから本文です。
自転車・歩行者の事故と道路の対策
島田土木事務所長 渡邉 良和 

- ※写真は10月31日のリバーフレンドシップの調印式の時の様子です(一番左が筆者)
日中の日差しは暖かですが、朝晩の冷え込みがはっきりと感じられるようになってきました。皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
今回は、歩行者対自転車の事故多発についてのお話です。
◆“自転車は車道を走るもの”という交通ルール
最近、歩道における歩行者対自転車の事故が急増しています。
その主な原因として、道路交通法で車道を走ることが原則とされている自転車が歩道を走っているから、というものや、最近、ブレーキの付いていない競技用自転車(もちろん公道を走ることは禁止されています)が急速に増加しているから、というものがあります。
皆さまは、この1つ目に挙げた“自転車は車道を走ることが原則”というルールをご存知だったでしょうか。以前から知っていたよ、という方はおそらく少ないのではないでしょうか。
その理由は、次のように考えられます。
本来、自転車は、歩道ではなく車道を自動車と並んで走るべきであるが、わが国の道路事情からそれでは交通事故の危険が増すうえ、自動車の円滑な走行にも影響を与える。西洋諸国のように自転車専用の通行帯をつくるべきだが、自転車通行帯をつくるための用地の確保は極めて困難だ。であれば、広めの歩道をつくって、その中を歩行者と一緒に、自転車にも徐行して通行してもらうのがいいだろう。
ということで、これまで交通事故防止の観点から、自転車と歩行者が混在して利用する“自転車歩行者道”の整備が積極的に進められてきました。そして、そのような広めの歩道は交通ルールを定める道路交通法に基づき、「自転車走行可」の指定がなされ、標識が立てられていることが一般的です。こうして、自転車に乗る人の多くは、“自転車は安全な歩道を走るのが当然”と考えてきたわけです。
しかし、今、競技用自転車の歩道違反走行は論外としても、歩道で徐行するべき自転車がわがもの顔でスピードを出して通行し、しかも一旦停止も十分にしない、などにより、歩行者に危害を加える事故が急増しているという構図が出来ています。
◆歩行者、自転車の事故防止に向けて…警察(交通管理者)
そこで、警察庁(交通管理者)は、この10月25日に、「歩道は歩行者優先であり、例外的に自転車が走行する場合はルールを徹底する。これまで歩道幅2m以上で自動車走行を認めていたが、今後は3m未満の歩道については原則として自転車走行を認めないよう見直す。」旨の通達を出しました。
その際、車道部を走行する自転車の安全に配慮して、警視庁では東京都内の道路について、車道左側の歩道に隣接する部分を、自転車通行帯として新たに路面表示することを公表しました。
◆歩行者、自転車の事故防止に向けて…島田土木事務所(道路管理者)
この問題に対する、私どもの管理する道路における対応は次のとおりです。
まず、これまでの状況を再確認しておきます。
最も望ましい形は、道路のどの場所を使うにせよ、自転車通行帯を設けることですが、これまで、道路や沿道の状況から自転車通行帯の設置スペースがなかなか確保できないため、自転車と歩行者が混在して通行する自転車歩行者道の整備を積極的に進めてきたという状況でした。
今後は、この混在する自転車と歩行者を、如何に分離するかということになります。
なお、一般的な自転車歩行車道の幅は、最小2.5m、広いもので4.5~5.5mとなっています。この幅の中から、自動車の指定速度や駐車禁止などの標識を歩道内に設置するための幅0.5mを生み出したり、街路樹を植えるための幅0.5~1.5mを生み出したりしています。したがって、自転車と歩行者が実質的に利用できる幅は、植樹帯などを除いた2.0m~4.0mということになりますが、大部分は2.0m~3.0mというところです。
このような状況の中で危険性をできるだけ早く減少させるのに、どのような方法があるのでしょうか。歩道が設置されている、または設置が予定されている場合では、
- 通行可能幅3.0mが確保されている歩道では、幅を2分割し、歩行者と自転車の通行帯を分離する。ただし、それぞれの通行帯の幅が十分かどうか、通行量も見ながら判断する必要がある。
- 植樹帯がある歩道では、植樹帯を取りやめ、または縮小して、分離された広めの歩行者と自転車の通行帯とする。
- 幅が3.0m未満の狭い歩道で、歩行者と自転車の通行帯を分離することが困難な場合は、車道左側の歩道に隣接する部分を自転車通行帯とする。ただし、十分な通行幅が確保できるケースは少ない。
当事務所が管理する道路のうち、自動車や歩行者が通行することのできる道路は市街地部、平地部、山地部のすべてを合わせて、51路線636kmです。この中に、自転車歩行者道が321km、歩行者のみが通行可の歩道が84km設置されています(どちらも延べ延長で、両側に設置されている場合は2倍となります)。緊急的に効果を上げるためには、自転車歩行車道の設置されている、または設置が予定されている区間の対策を実施することが、最も現実的と思われます。
私どもは、上に挙げた方法に、考えられる別の選択肢を加え、警察や地域の皆さまと十分に話し合ったうえで、各地域における最適な対応策を判断していくことになります。
◆時代とともに変わる“重要課題”
私どもが道路をつくる際の設計基準である「道路構造令」では、改訂時も含め、現在のような自転車と歩行者との事故の頻発までは、特に想定はされていなかったと考えられます。また、道路やまちの景観向上を重視する観点から、バブル経済が破綻した後も長い間、街路樹の植樹帯設置が重要視されてきました。
どんな分野においても、世の中が移り変わりゆく中で、その時々の社会的な最重要課題は変化していきます。現在の社会では、交通事故ゼロに向けた取組みの中で、特に自転車と歩行者との事故が重要な問題となっています。また、一方で、わが国経済の逼迫の中、高齢化した道路舗装や橋梁などの、公共施設の維持管理予算の確保が重い課題となっています。街路樹の維持管理においてもまったく同様です。
自転車と歩行者との事故の減少に向けては、もちろん自転車に乗る人のマナーが最も重要ですが、私どもの立場から、この課題に対してどのような対策を行うのが総合的に最適であるのか、将来をしっかり見据え、皆さまと一緒に考えながら、着実に対策を実行していきたいと考えています。
それでは皆さま、またお会いする日まで、お元気でお過ごしください。
平成23年11月8日
島田土木事務所長 渡邉 良和