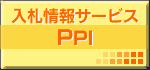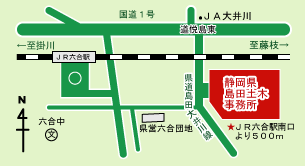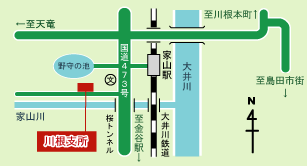ここから本文です。
台風と風の力
- 島田土木事務所長 渡邉 良和

- ◆立木を倒す風の力
皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
前回、私どもの管理する施設における今年の台風被害のお話をしましたが、今回はその続編です。
今年の台風は、当事務所管内の最多降雨量が、いずれも本川根観測所で台風6号が532mm、台風12号が739mm、そして台風15号が426mmと、どの台風もかなりの雨を降らせましたが、このうち台風15号については、特に強風の被害が各地で顕著でした。
県内のいたるところで倒木が発生し、その影響で停電も起きてしまいましたが、当事務所の管理する道路でも、ひどい所では、わずかな区間内で40~50本の木が電線や路面に倒れ込むなどして、8路線9箇所で全面通行止めとなりました。
道路脇の電線にかかる倒木は、電線を管理する中部電力やNTTに撤去していただかなければならず、どちらの会社も処理しなければならない現場を多く抱えることから、なかなか全ての現場に手が回らないため時間がかかり、現在でも、県道伊久美元島田線の島田市大草地区で通行止めが解けない状況です。
皆さまがいつも目にする道路標識も、設置に際しては風の力を考えておく必要があります。たとえば、皆さまが道路から見上げる青色の大型道路案内標識は、文字数などにより板のサイズが異なり畳で3~4枚分の大きさになることも多いのですが、設計上、最も重要な要素は風の力です。
設計では、風速50m/秒に耐えられるように計算し、板の厚みやフレームのサイズ、支柱の太さを決めるとともに、地中に隠れるコンクリート基礎の形やサイズを決めます。この風速50m/秒という値は、今回の台風の風速と比べると設計にあまり余裕がないようですが、実は、“安全率”という考え方の中で、限界値に余裕を持たせるように設計し、しかも、それぞれの部材の製作時に、製品のばらつきを考慮して実際の強度が設計強度を上回るよう作られているので、実際に壊れたり倒れたりすることはまずありません。まれに標識が風などで倒れることがありますが、その原因は、年月を経て、見えにくいところで部材が錆びていたり、ねじが緩んでいたりというのがほとんどです。
私ども公共施設を管理する者は、高度成長期を中心に整備された多くの公共施設に対して、こまめに点検し、より経済的に維持管理を行っていく責務があります。道路標識もこうした中で、しっかり管理していきます。
◆吊り橋とゼロ戦
さて、風に関するお話をしてきましたが、少し違う視点からの風のお話をします。
アメリカ合衆国に「タコマナローズ橋」という橋(以下「タコマ橋」と呼ぶ)があります。ワシントン州の海峡に架かるこの橋は、2007年に開通した現在の橋は3代目ですが、初代の橋に関しては、土木技術を学んだ者は誰でも知っているはずのエピソードがあります。
初代のタコマ橋は、1940年7月1日に開通した全長1,600mの吊り橋ですが、開通して約4ヵ月後の11月7日に落橋してしまいました。風速19m/秒の横風により、ケーブルに吊られた薄い板状の橋桁(道路面を載せている構造部分)が、桁の上下に交互に発生する風の渦により激しく揺れて、落橋に至ったものです。私も大学の講義の中で、タコマ橋の揺れが増幅されて激しく揺れ、ついに落橋するまでの様子が撮影されたビデオを観て、本当にショックを受けたものです。
この風の渦による揺れ(振動)は、風が吹くと電線が鳴ったり、旗がバタバタとはためく現象と同じもので、土木工学や機械工学などの分野における「流体力学」の中で学びます。旗がバタバタしたり、タコマ橋のように揺れが増幅される現象は「フラッター現象」と呼ばれるもので、物体の共振とも呼ばれます。
タコマ橋については、2代目の橋が、風の影響を受けにくくするように改善された設計で建設されて1950年10月に開通し、1日当たり6万台の交通を担って活躍していましたが、その後時代が移り、9万台/日(2005年)に達するほどの交通量になったことから、現在の橋が建設されたそうです。
なお、わが国の、本州と四国を結ぶ明石海峡大橋や大鳴門橋を始めとする現在の吊り橋は、タコマ橋の教訓を受けて、橋桁を撓みにくい構造にしたり、風が通り抜けやすい構造にするなどの対策が講じられており、十分に安全なものとなっています。
また、いつも我々が目にする、もっと橋長の短い多くの橋は、元々、橋桁に重量があるため風による落橋の心配はありません。
次は、かの「ゼロ戦」も風への対応に苦労したというお話です。
太平洋戦争で活躍したゼロ戦の設計では、飛行速度と飛行距離を向上させるとともに、敵機との空中戦(ドッグファイト)を有利にするため、極限までの軽量化を図りました。そして設計時に主翼の板厚を0.5mmとして試験飛行をしたところ、フラッター現象により主翼が波打ち、2度にわたって機体が空中分解してパイロットが命を落としたそうです。結局、板厚0.6mmに剛性を増して解決したそうです。
余談ですが、ゼロ戦は軽量化のために人命を犠牲にしていました。機体の板厚のほかに、相手側飛行機が燃料タンクを2重にして中にゴムを挟み、被弾しても発火しない構造にしたり、パイロットの命を守るために風防ガラスを防弾ガラスにしていたのに対して、ゼロ戦はどちらも余分な対策なしです。そのためゼロ戦は、運動性能に優れ、最初は向かうところ敵なしだったのですが、その後、機体の性能に劣っていた相手側が、エンジンの馬力を向上させて性能を向上させるとともに、墜落したゼロ戦を徹底的に調べ上げて燃料タンクや風防ガラスの欠点に気がつき、その後の空中戦ではすぐに火が点くゼロ戦の燃料タンクを狙い撃ちにして、力関係を逆転させたのだそうです。
2回にわたり、台風や風の被害、風の力について、お話をさせていただきました。
それでは、お元気でお過ごしください!
平成23年10月6日
島田土木事務所長 渡邉 良和